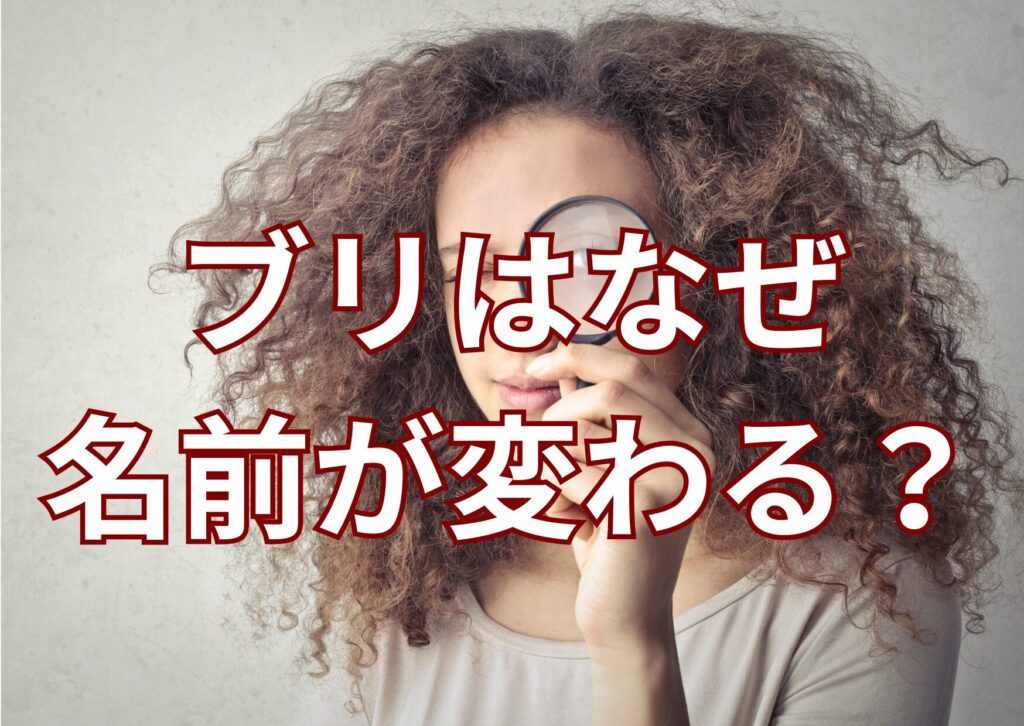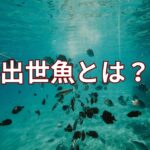ブリは出世魚の代表といわれるほど、成長によって呼び名が大きく変化する魚です。
「ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ」という変化は、聞いたことがある人も多いかもしれません。
では、なぜ名前が変わるのでしょうか?
ここでは、成長段階の一覧、地域差、語源、味わいの変化まで、わかりやすく解説します。
ブリの出世魚名(成長段階一覧)
| 成長段階 | 呼び名(主に関東) | 呼び名(主に関西) |
|---|---|---|
| 小型(約20cm未満) | ワカシ | ツバス |
| 中型(30cm前後) | イナダ | ハマチ |
| 40〜60cm | ワラサ | メジロ |
| 成魚(60cm〜) | ブリ | |
同じ魚なのに、地域によって呼び名が大きく変わる点が、ブリの面白いところです。
なぜ名前が変わるのか?
理由は、漁師や市場での取り引きや品質呼び分けのためです。
- 小さい → 身が淡い → 価値は低い
- 大きい → 脂がのる → 価値が高い
この「価値の変化」を、名前の違いで示してきたことが出世魚の由来です。
名前が変わる → 価値が上がる → 出世に例えられた
語源・歴史に見る「ブリ」の意味
「ブリ」の語源は「古(ふる)→ ぶる → ブリ」といわれ、大きく成長した成熟魚を意味した、という説があります。
また、江戸時代にはすでに「ブリは出世の象徴」とされ、 正月料理や祝い膳に使われる文化が生まれました。
味わいの変化
- ワカシ / イナダ: さっぱりとして淡白、刺身より焼き・照り焼き向き
- ワラサ: 脂のりが良く、刺身にも向く
- ブリ: 旨味と脂が強く、刺身・しゃぶしゃぶ・照り焼きに最適
成長するほど味も濃くなるため、料理の使い分けもできます。
まとめ
ブリは成長段階に応じて呼び名が変わる、出世魚の象徴的な存在です。
成長とともに味わいも価値も変化していく姿は、日本の食文化の中で大切に受け継がれてきました。