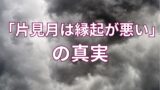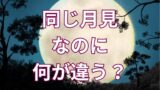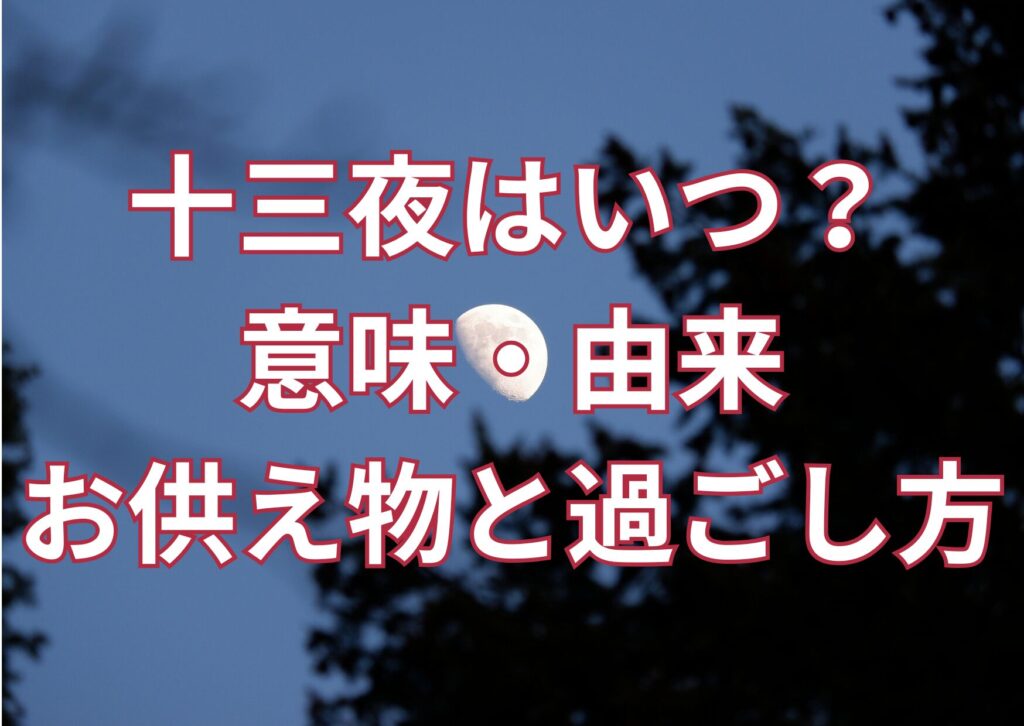「十三夜(じゅうさんや)」という月見行事をご存知ですか?
中秋の名月(十五夜)は有名ですが、実は日本には「十三夜」というもう一つの美しい月見の伝統があります。
2025年の十三夜は11月2日(日曜日)です。
この記事では、十三夜について以下の内容を詳しく解説します:
- 十三夜とは何か?意味と由来
- 2025年の十三夜の日付と見頃時間
- 十五夜との違いと「後の月」の意味
- お供え物(団子・栗・豆)の準備方法
- 片見月とは?なぜ縁起が悪いのか
- 現代での十三夜の過ごし方
十三夜は日本独自の美しい伝統行事です。
2025年の十三夜を楽しむために、ぜひこの記事をチェックしてみてください!
十三夜とは?基本情報
十三夜の定義
十三夜(じゅうさんや)は、旧暦9月13日の夜に月を鑑賞する日本の伝統行事です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 十三夜(じゅうさんや) |
| 別名 | 後の月(のちのつき)、栗名月、豆名月 |
| 時期 | 旧暦9月13日(新暦10月〜11月頃) |
| 月齢 | 月齢約13(やや欠けた月) |
| 起源 | 日本独自の行事 |
2025年の十三夜はいつ?
2025年の十三夜は11月2日(日曜日)です。
| 年 | 十三夜の日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 2025年 | 11月2日 | 日 |
| 2026年 | 10月22日 | 木 |
| 2027年 | 11月10日 | 水 |
十三夜の日付は旧暦に基づくため、毎年変動します。
なぜ「十三夜」なのか
名前の由来:
旧暦9月13日の夜、つまり新月から数えて13日目の夜だからです。
月齢約13の月を愛でる行事です。
満月ではない理由:
十三夜の月は満月(十五夜)より少しだけ欠けています。
この「少し欠けた月」が、日本人の美意識である「不完全の美」を表していると言われています。
👉なぜ満月じゃない「十三夜」を愛でるの?|日本独自の月見文化と美意識
十三夜の意味と由来
日本独自の月見文化
十三夜の最大の特徴:
十三夜は日本で生まれた独自の月見行事です。
中国から伝わった中秋の名月(十五夜)とは異なり、日本で発展した文化です。
起源:
平安時代の宇多法皇(在位887-897年)が、旧暦9月13日の月を愛でたことが起源とされています。
醍醐天皇の時代(延喜19年・919年)には、観月の宴が開かれた記録があります。
「後の月(のちのつき)」とは
十三夜は「後の月」とも呼ばれます。
意味:
中秋の名月(十五夜)の「後に来る月見」という意味です。
時期:
- 十五夜(中秋の名月): 旧暦8月15日(9月中旬〜下旬頃)
- 十三夜(後の月): 旧暦9月13日(10月〜11月頃)
十五夜の約1ヶ月後に訪れます。
「栗名月」「豆名月」の由来
十三夜は「栗名月(くりめいげつ)」「豆名月(まめめいげつ)」とも呼ばれます。
理由:
旧暦9月は栗や豆の収穫期にあたるため、これらをお供えする習慣があります。
農耕文化との関係:
十五夜が「芋名月」と呼ばれるのに対し、十三夜は秋の収穫を祝う行事としての意味合いが強いです。
十五夜(中秋の名月)との違い
基本情報の比較
| 項目 | 十五夜(中秋の名月) | 十三夜(後の月) |
|---|---|---|
| 時期 | 旧暦8月15日 | 旧暦9月13日 |
| 月齢 | 約15(満月) | 約13(やや欠けた月) |
| 起源 | 中国から伝来 | 日本独自 |
| 別名 | 芋名月 | 栗名月、豆名月 |
| お供え物 | 芋、団子、ススキ | 栗、豆、団子、ススキ |
| 2025年の日付 | 9月7日(日) | 11月2日(日) |
月の見え方の違い
十五夜:
- 満月(または満月に近い)
- まん丸で明るい
- 「完全な美」
十三夜:
- やや欠けた月
- 右側がわずかに欠けている
- 「不完全の美」「余韻の美」
日本人は完璧な満月よりも、少し欠けた月に趣を感じる美意識があります。
文化的な違い
十五夜:
- 中国の中秋節に由来
- 国際的な行事
- 豊作を祈る意味合い
十三夜:
- 日本で独自に発展
- 国内限定の行事
- 収穫に感謝する意味合い
片見月(かたみつき)とは
片見月の意味
片見月とは、十五夜と十三夜のどちらか一方しか見ないことを指します。
なぜ縁起が悪い?
古来より、片見月は「片方だけ」という不完全さから、縁起が悪いとされてきました。
両方見るべき理由
伝統的な考え方:
「十五夜と十三夜は対(つい)」であり、両方を愛でることで初めて完結すると考えられていました。
現代的な解釈:
両方の月見を楽しむことで、秋の深まりを十分に味わえます。
2025年の場合:
- 十五夜: 9月7日(日)
- 十三夜: 11月2日(日)
両方とも日曜日のため、予定が立てやすい年です!
片見月の由来
江戸時代の風習:
遊郭などで、十五夜に来た客を十三夜にも呼び戻すための口実として「片見月は縁起が悪い」という言い伝えが広まったという説もあります。
さらに詳しく👉片見月とは?十五夜と十三夜を両方見るのが縁起良い理由
お供え物の準備
基本のお供え物
十三夜のお供え物は、以下の3つが基本です:
- 月見団子
- 栗
- 豆(枝豆など)
- ススキ
月見団子
団子の数
伝統的には13個
十三夜にちなんで、13個の団子をお供えします。
並べ方:
| 段 | 個数 | 配置 |
|---|---|---|
| 1段目(下) | 9個 | 3×3 |
| 2段目(中) | 3個 | 三角形 |
| 3段目(上) | 1個 | 頂点 |
簡略版でもOK:
家庭では3個、5個など、できる範囲で構いません。
大切なのは感謝の気持ちです。
団子の作り方
材料(13個分):
- 上新粉:150g
- 白玉粉:50g
- 砂糖:大さじ2
- 水:適量
作り方:
- 粉類を混ぜ、水を少しずつ加えて耳たぶくらいの固さにする
- 一口大に丸める(13個)
- 沸騰したお湯で茹でる(浮いてきたら1分ほど)
- 冷水で冷やす
- お供えする
栗
なぜ栗?
旧暦9月は栗の収穫期です。「栗名月」の由来でもあります。
お供え方法:
- 皮付きのまま器に盛る
- 数は13個、または3個、5個など奇数
- 栗ご飯を作ってお供えする家庭も
豆
なぜ豆?
枝豆や大豆も旧暦9月の収穫期です。「豆名月」の由来です。
お供え方法:
- 枝豆を茹でてお供え
- 枝付きのまま飾ることも
- 豆ご飯を作る家庭も
ススキ
なぜススキ?
ススキは神様の依り代(よりしろ)とされ、魔除けの意味もあります。
飾り方:
- 月見台や窓辺に飾る
- 15本または13本(十五夜なら15本、十三夜なら13本)
- 稲穂で代用することも
注意点:
ススキの穂には細かい毛があるため、小さなお子さんやペットがいる家庭では注意が必要です。
2025年十三夜の見頃時間と方角
月の出と南中時刻
2025年11月2日(日)の月の動き(東京):
| 時刻 | 月の位置 |
|---|---|
| 16:20頃 | 月の出(東の空) |
| 21:30頃 | 南中(南の空で最も高い位置) |
| 翌2:40頃 | 月の入り(西の空) |
※地域により若干の差があります
おすすめ観賞時間
ベスト観賞時間:
20:00〜23:00
理由:
- 空が十分に暗くなっている
- 月が比較的高い位置にある
- 夕食後のゆったりした時間
方角
観賞する方角:
- 18:00頃: 東の空(やや低い)
- 21:30頃: 南の空(最も高く、美しい)
- 24:00頃: 南西の空
おすすめ:
南の空を向いて観賞するのが最も美しく見えます。
天気予報
2025年11月2日の天気は、10月下旬頃から確認できます。
「十三夜に曇りなし」:
古来より「十三夜は晴れやすい」という言い伝えがあります。
統計的にも、この時期は秋の高気圧に覆われやすく、晴天率が比較的高いとされています。
現代での十三夜の過ごし方
家庭で楽しむ
1. シンプルな月見
最小限の準備:
- お団子3個
- ススキ数本
- 窓辺に飾る
おすすめ:
マンションのベランダや窓際でも十分に楽しめます。
2. 家族で月見パーティー
メニュー例:
- 栗ご飯
- 枝豆
- 月見団子
- 秋の味覚(サンマ、きのこ料理など)
活動:
- 月を見ながら食事
- 子どもと一緒に団子作り
- 月にまつわる絵本を読む
3. 写真撮影
スマホでの撮影コツ:
- 夜景モードを使用
- 三脚やスマホスタンドで固定
- ススキと月を一緒に撮る
- 建物のシルエットと月を組み合わせる
神社・寺院のイベント
2025年の十三夜イベント例:
一部の神社や寺院では、十三夜の観月会が開催されます。
主な開催地(例):
- 京都の寺院(大覚寺など)
- 奈良の春日大社
- 東京の増上寺
※詳細は各施設の公式サイトで確認してください
SNSでの楽しみ方
ハッシュタグ:
- #十三夜
- #後の月
- #栗名月
- #豆名月
- #月見2025
投稿アイデア:
- 月とお供え物の写真
- 手作り団子の工程
- 栗ご飯・豆ご飯のレシピ
- 月の撮影写真
十三夜にまつわる雑学
日本だけの行事
十三夜は日本でしか行われていない珍しい月見行事です。
海外での月見:
- 中国: 中秋節(十五夜に相当)のみ
- 韓国: 秋夕(チュソク・十五夜に相当)のみ
- ベトナム: 中秋節(十五夜に相当)のみ
十三夜は日本独自の美意識が生んだ文化です。
十日夜(とおかんや)
十三夜の後、さらに「十日夜(とおかんや)」という行事もあります。
十日夜:
- 旧暦10月10日
- 主に東日本の農村部の行事
- 稲の刈り取りが終わった後の収穫祭
「十五夜・十三夜・十日夜」の3つを「三月見」と呼ぶ地域もあります。
平安貴族と十三夜
平安時代の貴族は、十三夜に船を浮かべて月を愛でたり、和歌を詠んだりしました。
有名な和歌:
「秋の夜の 月のひかりし 清ければ 影見し水ぞ 先づこほりける」 (古今和歌集)
月の美しさを水に映して楽しむ「水鏡」の風習もありました。
英語での説明
英語で十三夜を説明するなら:
“Jusanya: Japan’s unique moon-viewing tradition on the 13th lunar night of the 9th month, appreciating a slightly waning moon. It’s also called ‘the latter moon’ and celebrated about a month after the harvest moon.”
関連する行事
十五夜(中秋の名月)
十三夜と対をなす月見行事です。
2025年の十五夜: 9月7日(日)
片見月を避けるため、両方楽しみましょう。
秋分の日
秋分の日の前後も、月が美しい季節です。
2025年の秋分の日: 9月23日(火)
詳しくは👉【2025年秋分の日】いつ?意味・由来・連休パターンまで完全解説をご覧ください。
十日夜(とおかんや)
2025年の十日夜: 11月27日頃(旧暦10月10日)
東日本の農村部で行われる収穫祭です。
まとめ(FAQ付き)
Q1: 2025年の十三夜はいつですか?
2025年の十三夜は11月2日(日曜日)です。
Q2: 十三夜とは何ですか?
旧暦9月13日の夜に月を鑑賞する日本独自の月見行事です。
「後の月」「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。
Q3: 十五夜と何が違うのですか?
十五夜は満月を愛でる中国由来の行事ですが、十三夜は少し欠けた月を愛でる日本独自の行事です。
また、十五夜の約1ヶ月後に訪れます。
Q4: 片見月とは何ですか?
十五夜と十三夜のどちらか一方しか見ないことを「片見月」と呼び、縁起が悪いとされています。
両方を楽しむのが伝統です。
Q5: お供え物は何を用意すればいいですか?
基本は月見団子13個、栗、豆、ススキです。
家庭では簡略化してもOKです。
Q6: 十三夜は必ず13個の団子?
伝統的には13個ですが、家庭では3個、5個などに簡略化しても構いません。
大切なのは感謝の気持ちです。
Q7: 十三夜はなぜ晴れやすいと言うの?
「十三夜に曇りなし」という言い伝えがあり、季節的に秋の高気圧に覆われやすく、天候が安定しやすい時期だからとされます(地域差あり)。
Q8: 英語ではどう説明する?
“Jusanya: Japan’s unique moon-viewing on the 13th lunar night, appreciating a slightly waning moon.” と説明できます。
関連記事