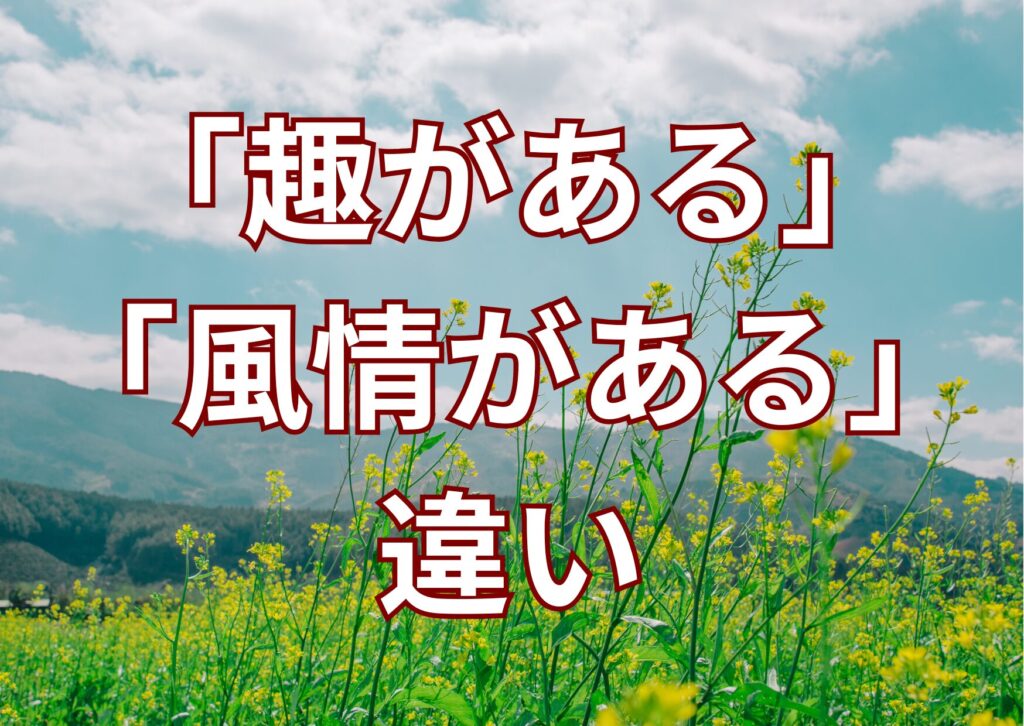🌸 「趣がある」って“内側の美”、じゃあ「風情がある」は?
紅葉を見て「風情があるね」と言ったり、古民家を見て「趣がある」と言ったり──
どちらも“しみじみとした良さ”を表す美しい日本語です。
でも実はこの2つ、同じようでいて違う角度の美を指しているんです。
⏱ 3分で読めます!
👉 「味がある人」ってどんな人?実は“欠点のある人”を褒めてる言葉だった!
“完璧じゃない魅力”をほめる、日本語の奥深さを解説。
🏯 「趣がある」とは?
意味は“内面からにじみ出る深み”
「趣(おもむき)」は、もともと“心が動かされる感じ”という意味。
つまり「趣がある」とは、見た目よりも中身・雰囲気の深みを感じる表現なんです。
たとえば古本屋の静けさ、年季の入った喫茶店──外見の派手さではなく、内面の静かな魅力を感じるときに使います。
「わび・さび」に通じる感覚
日本人が大切にしてきた「わび・さび」の心。
華やかさより“時間の重み”や“静かな味わい”を重視する考え方です。
「趣がある」はまさにこの精神を言葉にしたような表現なんですね。
🍁 「風情がある」とは?
意味は“外から見て情緒を感じる”
一方の「風情(ふぜい)」は、風や景色など外から見て感じる情緒や雰囲気を指します。
たとえば雪が降る夜、灯りに照らされた石畳──そんな“目に見える美しさ”を感じたときに使う言葉です。
五感で味わう“情景の美”
「風情がある」は、視覚や聴覚などの五感で感じる瞬間の美。
だから「風情のある旅館」「風情のある街並み」など、景色や状況に使われることが多いんです。
🌾 「趣」と「風情」の違いをまとめると?
内側と外側の美
- 趣がある → 内面の美しさ、時間や経験の深み
- 風情がある → 外から感じる情緒、景色の美しさ
同じ“静かな美”でも、感じる方向が真逆なんです。
例文でイメージしよう
- 「この喫茶店、古くて趣があるね」
→ その場の雰囲気・歴史が心に染みる - 「夕暮れの川沿い、風情があるね」
→ 目に見える情景の美しさを感じる
☕ 似てるようで違う、日本語の奥ゆかしさ
どちらも“静かな褒め言葉”
どちらも日本語らしい上品な褒め言葉。
日常でさらっと使うと、語彙のセンスが光る表現です。
英語にしづらいニュアンス
英語では「charming」「atmospheric」などが近いですが、「趣がある」「風情がある」ほど繊細な“情緒の美”は訳しきれません。
だからこそ、この言葉たちは日本語の美意識の象徴なんです。
✅ まとめ:「趣」は心で感じ、「風情」は目で感じる
- 「趣がある」= 内側の深み
- 「風情がある」= 外側の情緒
- どちらも“静かな美しさ”を表す日本語の代表格
覚えておきたい一言:「趣」は心に残り、「風情」は目に残る。
🔗 関連記事

「味がある人」ってどんな人?実は“欠点のある人”を褒めてる言葉だった!
「味がある人」とはどんな人?実は欠点を含めて魅力とする褒め言葉だった。意味・語源・使い方、誤解されやすいポイントや年代による受け取り方の違いまで、日本語雑学としてやさしく解説。

「絵になる」とは?意味・使い方と「画になる」との違いをわかりやすく解説
「絵になる」とは、見た目が美しく印象的な様子を表す慣用句。結論は「絵になる」が正しく、「画になる」は誤用です。なぜ混乱が広まったのか、20世紀の映像文化との関係や正しい使い方を解説します。