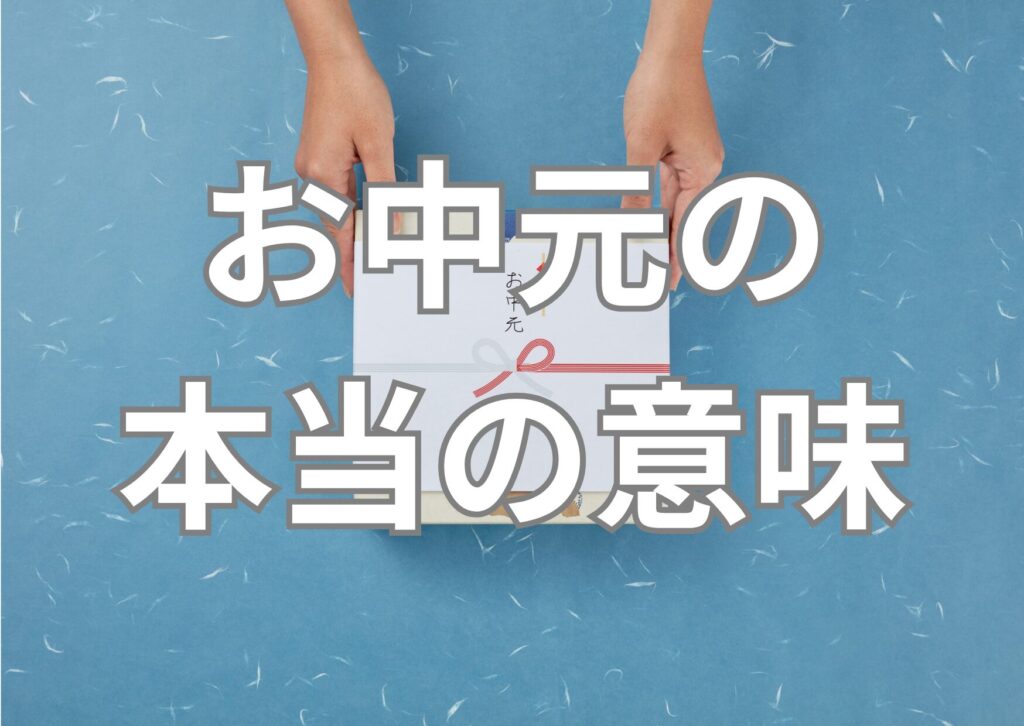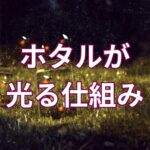お中元って、なんで贈るんでしょうね?
お世話になった人への感謝でしょ?って思ってませんか?
調べてみたら、想像もしてなかった宗教的で感動的な理由があったんです!
そもそもお中元って何?【基本のき】
お中元といえば、夏にお世話になった人に食べ物やビールを贈る習慣。
7月頃になると、デパートでお中元コーナーが設置されて、みんな何を贈ろうか悩みますよね。
でも、なんで「中元」っていう名前なの?
なんで夏なの?
そもそもいつから始まったの?
実はお中元って、単なる感謝の贈り物じゃなくて、罪を許してもらうための贈り物だったんです!
え?お中元の由来って○○だった!【真相解明】
理由その1:中国の道教「三元」が起源【宗教的ルーツ】
お中元の「中元」は、中国の道教の「三元」から来てるんです。
上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)の3つの神様の誕生日。
特に中元の神様「地官赦罪大帝」は、人間の罪を許してくれる神様として信仰されてました。
だからこの日にお供え物をすると、罪を赦してもらえると信じられてたんです!
理由その2:日本のお盆と結びついた【文化の融合】
この中国の風習が日本に伝わって、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と結びつきました。
先祖供養の意味も加わって、お供え物を親戚や近所の人と分け合う「供食(きょうしょく)」の習慣が生まれたんです。
最初は家族間でのお供え物の分け合いだったのが、だんだん感謝の贈り物に変化していったんですね。
理由その3:江戸時代に商人文化と融合【現代への橋渡し】
江戸時代、商人たちの決算時期が夏と年末の2回。
夏の決算時期にお得意先を回って、半年間のお礼として手ぬぐいなどの粗品を配ってたんです。
この商慣習と中元の贈り物文化が結びついて、現在の「お世話になった人への感謝の贈り物」になったんですよ!
まだあった!お中元の面白すぎる豆知識【追い打ち情報】
豆知識1:もともとは贖罪のための行事【深い宗教性】
最初は「神様に罪を許してもらう」ための真剣な宗教行事だったんです。
現在の「ありがとう」の気持ちとは全然違う、もっと深刻な意味があったんですね。
豆知識2:明治時代に百貨店が広めた【商業の力】
現在のようなお中元文化が定着したのは、明治30年代。百貨店が夏の売上アップのために大々的にお中元商戦を展開したのがきっかけなんです。
豆知識3:地域によって時期が違う【面白い多様性】
関東は7月、関西は8月、沖縄は旧暦…
地域によってお中元の時期が違うのも、それぞれの地域のお盆の時期に合わせてるからなんです。
【まとめ】お中元の意味、想像以上に深すぎた!
いかがでしたか?
お中元の本当の意味、想像してたより宗教的で深刻でしたよね!
単なる感謝の贈り物だと思ってたけど、そこには「罪を許してもらいたい」という切実な祈りが込められてたなんて。
しかも中国の道教、日本の仏教、江戸時代の商慣習が混ざり合って現在の形になったって、文化の融合ってすごくないですか?
今度お中元を贈る時は、「これは1000年以上続く文化の結晶なんだ」って思いながら選んでみてください。
きっといつもより特別な気持ちで贈れるはずです!