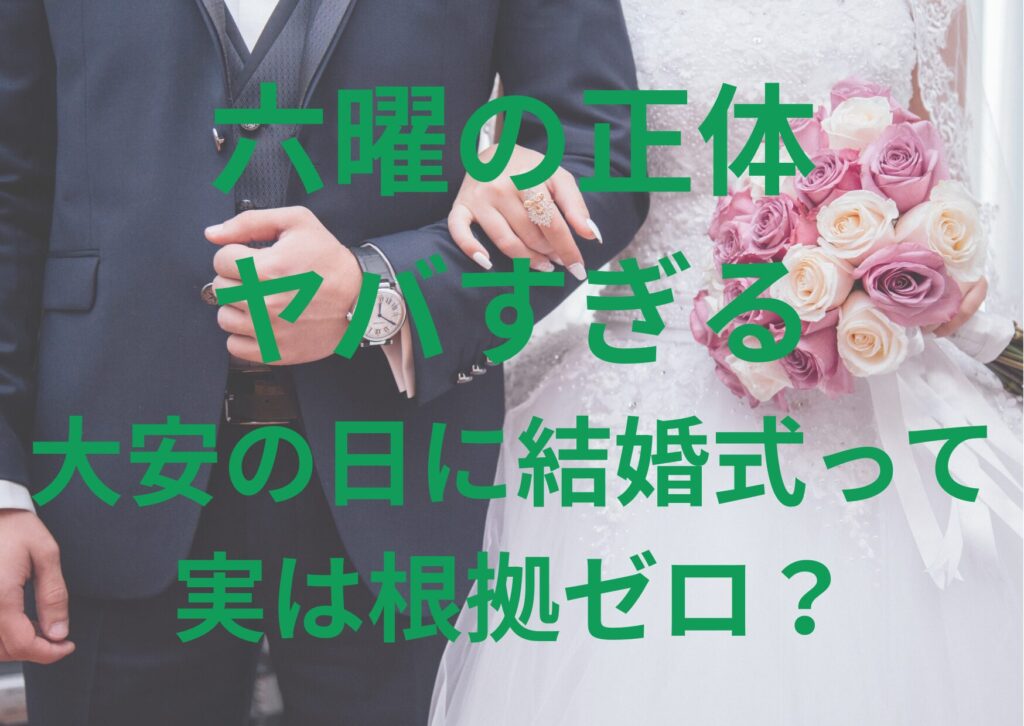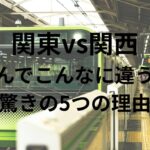「今度の結婚式、大安の日だから安心だね!」
「お葬式が友引だと、友達も引っ張られちゃうからダメ」って聞いたことありませんか?
でも、ちょっと待ってください!この大安や仏滅といった「六曜」、調べてみたら想像以上にヤバい正体が判明したんです。
みんなが信じてる根拠、実は…え?マジで?って感じの真実があったんですよ!
最後まで一緒に、この現代日本の不思議な迷信を解き明かしてみませんか?
そもそも六曜って何だっけ?【基本のき】
六曜というのは、カレンダーによく書いてあるアレです
- 大安(たいあん) – 何をするにも良い日
- 友引(ともびき) – 友達を引っ張る?から葬式はダメ
- 先勝(せんしょう) – 午前中が良い
- 先負(せんぷ) – 午後が良い
- 赤口(しゃっこう) – あまり良くない日
- 仏滅(ぶつめつ) – 最悪の日、結婚式は絶対避ける
この6つが順番に繰り返されていて、「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口→先勝…」というサイクルになってます。
結婚式場でも「大安は高い、仏滅は安い」って料金体系があったり、引っ越し業者も「大安は忙しい」なんて言いますよね。
でも、これって本当に意味があるんでしょうか?
え?六曜の正体って実は超テキトーだった!【真相解明】
理由その1:もともと時刻の占いで曜日関係なし【大誤解の始まり】
実は六曜、最初は「曜日の吉凶」じゃなかったんです!
中国から伝わってきた当初は「時刻の吉凶」を決めるもので、「今日の午前中は先勝だから良い時間帯」みたいな使い方をしていました。
つまり、1日の中の時間を6つに分けて、どの時間が良いかを判断する占いだったということです。
それがいつの間にか「その日全体の吉凶」に変わっちゃったんですよ。
これ、めちゃくちゃ大きな変化じゃないですか?
「友引だから友達が引っ張られる」って、元々は「友引の時刻だから」という話だったのに、「友引の日だから」に変わってしまったんです。
理由その2:江戸時代の庶民が勝手にアレンジ【民間流行の暴走】
六曜が日本に定着したのは江戸時代なんですが、この時に庶民が勝手に解釈を変えちゃったんです。
特に「友引」なんて、元々は「共引」という字で「勝負がつかない」という意味だったのに、いつの間にか「友を引く」になって「友達を道連れにする」という恐ろしい解釈に変わりました。
「仏滅」も元々は「物滅」で「物事がうまくいかない日」だったのに、「仏」の字が付いたせいで宗教的な意味があると勘違いされるようになったんです。
江戸時代の人たち、想像力豊かすぎでしょ!
でも、その想像力で現代まで影響を与えているって考えると、ある意味すごいですよね。
理由その3:明治政府も困った「迷信禁止令」【政府vs民間の攻防】
明治時代になると、政府は「六曜は迷信だから禁止!」って言い出しました。
「科学的根拠のない迷信で国民が振り回されるのはよくない」ということで、暦から六曜を削除したんです。
でも、庶民は「そんなこと言われても…」って感じで、こっそり六曜を使い続けました。
結局、政府も諦めて昭和時代には暦に復活。
現在に至るまで、堂々と大安や仏滅が書かれているという状況です。
つまり、明治政府ですら止められなかった庶民パワーってことですよね。
ある意味、六曜の生命力すごすぎます!
まだあった!六曜の面白すぎる現代事情【追い打ち情報】
豆知識1:結婚式場の料金設定は完全に商売【ビジネス化された迷信】
現代の結婚式場やホテルの料金って、六曜で露骨に変わりますよね。
大安:一番高い → 友引:普通 → 先勝・先負:少し安い → 赤口:安い → 仏滅:激安
でも冷静に考えてください。
ホテルのシェフが大安の日に特別においしい料理を作るわけじゃないし、大安の日の花が特別にキレイに咲くわけでもありません。
つまり、まったく同じサービスなのに、カレンダーの文字だけで値段が変わってるということです。
これ、よく考えたらすごいビジネスモデルじゃないですか?
豆知識2:友引の日の火葬場は本当に休み【迷信の制度化】
「友引の日に葬式をすると友達も死ぬ」という迷信、まさか本気で信じてる人はいないと思いますが…
火葬場は本当に友引の日を定休日にしているところが多いんです!
これ、火葬場の職員さんも「科学的根拠はないけど、みんなが嫌がるから仕方なく」っていう感じらしいです。
現代の合理的なシステムの中に、江戸時代の迷信がガッツリ組み込まれてるって、なんか不思議な光景ですよね。
豆知識3:六曜を気にしない人が実は増えてる【世代間ギャップ】
最近の若い世代では、六曜を気にしない人が急増しています。
「大安?仏滅?別によくない?」「好きな日に結婚式挙げればいいじゃん」という感覚の人が多くなってるんです。
特にコロナ禍で「日程変更が大変だから六曜なんて気にしてられない」という現実的な判断をする人も増えました。
でも、親世代や祖父母世代は「やっぱり大安がいいんじゃない?」って言うので、家族間での調整が大変になるケースも。
現代の六曜は「迷信」というより「世代間コミュニケーションの課題」になってるのかもしれませんね。
【まとめ】六曜の真実、スッキリ解決!
いかがでしたか?
普段なんとなく気にしている六曜に、こんなにテキトーで人間的な歴史があったなんて面白かったですよね!
要点をまとめると
- 六曜はもともと時刻の占いで、日の吉凶じゃなかった
- 江戸時代の庶民が勝手に解釈を変えて現在の形になった
- 明治政府が禁止しても止められないほど庶民に浸透
- 現代では完全にビジネス化されて、火葬場まで休みにしてる
つまり、私たちが気にしている六曜は、何百年もかけて庶民がアレンジし続けてきた「みんなで作った迷信」だったということです。
科学的根拠はゼロだけど、日本人の文化として定着している。
それはそれで、人間らしくて面白いじゃないですか?
今度「大安じゃないとダメ」って言ってる人を見かけたら、「実は江戸時代の人たちの想像力の産物なんだよ」って教えてあげてください。
「へぇ〜そうなんだ!でもやっぱり大安がいいかな…」って言われるかもしれませんが、それはそれで日本らしくて素敵ですよね!