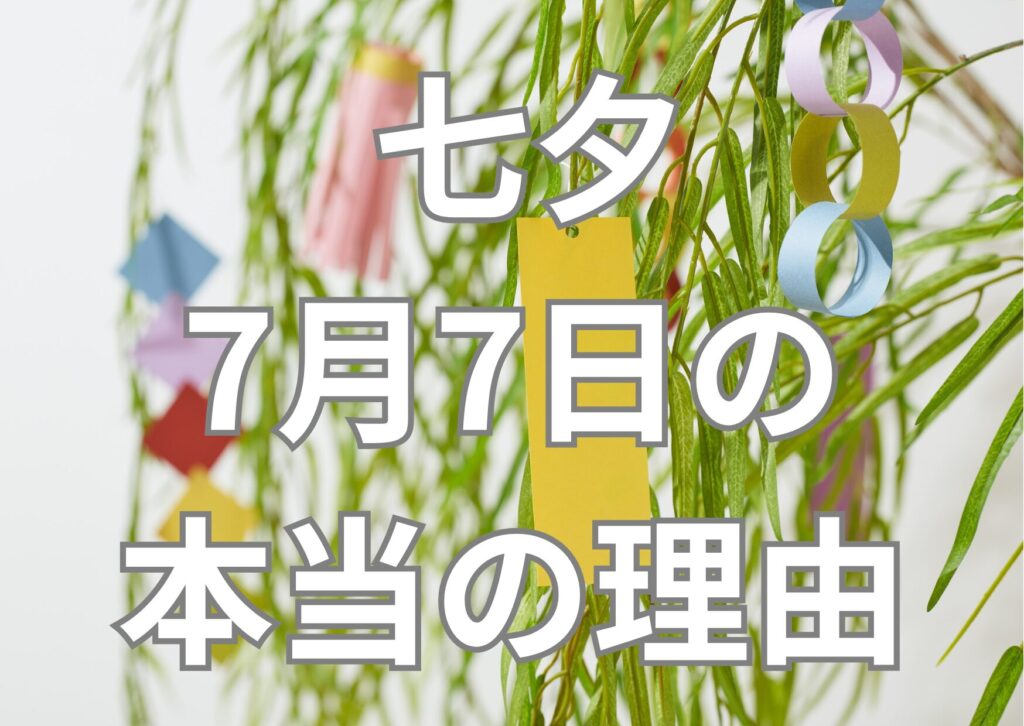七夕って、なんで7月7日なんでしょうね?
織姫と彦星の話は知ってるけど、なんで「この日」なの?って疑問に思いませんか?
調べてみたら、もっと深〜い理由があったんです!
そもそも七夕って何の日?【基本のき】
みんな知ってる織姫と彦星の恋物語。
年に一度だけ天の川で会える日として有名ですよね。短冊に願い事を書いて笹に飾るのも、日本の夏の風物詩です。
でも実は、七夕って「たなばた」と読むのに「七夕」って漢字を使うのも不思議じゃないですか?
しかも、なぜよりによって7月7日なのか…
実はこれ、単純に織姫と彦星の話だけじゃなかったんです!
え?7月7日になった理由って実は3つの文化が混ざってた!【真相解明】
理由その1:中国の「乞巧奠」という行事【みんなが思ってるアレ】
まず一つ目は、中国から伝わった「乞巧奠(きっこうでん)」という行事。
7月7日に織姫星にあやかって、裁縫や手芸の上達をお願いする風習があったんです。
「なるほど、それで織姫の話と繋がるのか〜」って思いますよね。
でも、まだ序の口なんです!
理由その2:日本古来の「棚機津女」の神事【ちょっと意外な話】
二つ目がこれ。日本には元々「棚機津女(たなばたつめ)」という、川辺で機織りをして神様をお迎えする神事があったんです。
この「棚機(たなばた)」という言葉が、「七夕」という漢字にあてはめられて「たなばた」と読むようになったんですって!
え?そういうことだったの?って驚きませんか?
理由その3:旧暦の7月7日は秋だった【一番驚きの真実】
ここからが本当にびっくりなんですが…
昔の暦(旧暦)では、7月7日って実は秋だったんです!
現在の8月下旬頃にあたるので、天気も良くて星がよく見える時期。
だから星のお祭りにピッタリだったんですね。
現在の7月7日は梅雨真っ只中で星が見えないことが多いのも、これが理由だったんです。
マジで目からウロコでした!
まだあった!七夕の面白すぎる豆知識【追い打ち情報】
豆知識1:七夕は年に3回ある【驚きの現代事情】
実は今でも、旧暦7月7日、新暦7月7日、月遅れの8月7日と、年に3回七夕があるんです。
仙台の七夕祭りが8月なのもこのため!
豆知識2:短冊の色にも意味があった【歴史的発見】
短冊の5色(赤・青・黄・白・黒)は、中国の五行思想から来てるんです。
それぞれに願い事の種類が決まってたなんて、知ってました?
豆知識3:そうめんを食べる風習もある【意外な裏話】
七夕にそうめんを食べる地域があるのも、中国の「索餅(さくべい)」という小麦のお菓子が由来。
天の川に見立ててるんですって!
【まとめ】七夕の7月7日、深すぎる理由が判明!
どうでしたか?七夕が7月7日の理由、想像してたより複雑でしたよね!
中国の星祭り、日本の神事、そして旧暦の季節感…3つの文化が絶妙に混ざり合って、今の七夕が生まれてたなんて。
しかも本来は秋の行事だったって、これは知らなかった人多いんじゃないですか?
今度七夕の日には、「この日には3つの文化が込められてるんだ」って思いながら短冊を書いてみてください。
なんだか願い事も叶いそうな気がしませんか?
次回は「海の日がなぜ7月20日だったのか」の意外すぎる理由を大公開します。
明治天皇が関係してるって、想像つきます?