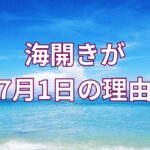土用の丑の日のうなぎって、江戸時代の販促戦略だったの?
7月になると、コンビニでもスーパーでも「土用の丑の日」の文字が踊りますよね。
でも、なんで土用の丑の日にうなぎを食べるようになったか知ってます?
実は、これって現代で言うところの「マーケティング戦略」が大成功した結果なんです。
しかも、その仕掛け人は江戸時代の超有名人だったんですよ。
土用の丑の日とは?基本的な概要
まず「土用の丑の日」について簡単に説明しますね。
「土用」というのは、季節の変わり目の約18日間のこと。
立春、立夏、立秋、立冬の前に、年4回あります。
その中で「丑の日」(十二支の丑)に当たる日が「土用の丑の日」です。
昔から、この時期は体調を崩しやすいので、「う」のつく食べ物(梅、うり、うどんなど)を食べて体を養生する習慣がありました。
でも、なんでうなぎが代表格になったんでしょうか?
なぜうなぎが選ばれたの?平賀源内の天才的アイデア
理由1:夏のうなぎは「売れない商品」だった
実は、うなぎの旬は秋から冬なんです。
脂がのって一番美味しい時期は10月から12月頃。
天然うなぎは、この時期に産卵に備えて栄養をたっぷり蓄えるからです。
だから江戸時代の夏場、うなぎ屋さんは大困り。
お客さんがぜんぜん来ないんです。
「夏にうなぎなんて食べたくない」「こってりしすぎて食欲がわかない」って感じだったんですね。
今でいう「季節外れの商品」を抱えて困っている状況だったわけです。
理由2:平賀源内のマーケティング・コンサルティング
そこで、あるうなぎ屋の主人が相談したのが、当時の超有名人・平賀源内でした。
平賀源内って、発明家で学者で蘭学者で、今で言うマルチタレントみたいな人だったんです。
源内は考えました。
「丑の日だから『う』のつくものがいいんでしょ?うなぎも『う』がつくじゃない!」
これって、現代でいう「既存の習慣に新商品を結びつける」という手法ですよね。
理由3:「本日土用丑の日」という革命的キャッチコピー
そして源内が提案したのが、店先に「本日土用丑の日」という張り紙を出すこと。
これが大当たり!
見慣れない言葉に足を止めたお客さんに、店主が源内直伝の口説き文句で説明すると、お店は大繁盛したんです。
「丑の日には『う』のつく食べ物がいいんです」「うなぎは夏バテに効きますよ」って感じで。
現代のマーケティングとの共通点
共通点1:「理由づけ」の重要性
現代のマーケティングでも「なぜその商品を買うべきか」の理由づけは超重要ですよね。
平賀源内は「丑の日だから」「夏バテ防止だから」という明確な理由を与えたんです。
バレンタインのチョコも「愛を伝えるため」、クリスマスケーキも「特別な日を祝うため」って理由がありますよね。
共通点2:「季節感」の活用
特定の日に特定の商品を結びつける手法。
これって現代でも使われまくりです。
母の日のカーネーション、敬老の日のプレゼント、ひな祭りのちらし寿司などなど。
共通点3:「話題性」で注目を集める
「本日土用丑の日」という見慣れない張り紙で、まず注目を集める。
これも現代の「バズマーケティング」に通じるものがあります。
SNSでバズる投稿も、まず「あれ?これなんだろう?」って注目を集めるところから始まりますよね。
世界各国の夏バテ対策食品
日本以外の国でも、夏の暑さ対策として特別な食べ物があります。
韓国では参鶏湯(サムゲタン)、中国では緑豆スープ、インドではヨーグルト系の飲み物など。
でも、特定の日に決まった食べ物を食べる習慣を作り出したのは、日本のうなぎが珍しい例かもしれませんね。
関連する面白い豆知識
豆知識1:他のうなぎ屋も真似しまくった
源内のアイデアが成功すると、他のうなぎ屋も「うちも土用の丑の日やります!」って真似しまくり。
江戸中のうなぎ屋が同じキャッチコピーを使うようになって、それで全国に広まったんです。
現代のトレンドの広がり方とそっくりですね。
一つのお店が成功すると、みんなが真似して定番になる。
豆知識2:万葉集にもうなぎの夏バテ解消効果が
実は奈良時代の万葉集にも「夏痩せに良しといふものぞ鰻とり食せ」という歌があるんです。
大伴家持が友人に「夏バテにはうなぎがいいよ」って勧めた歌なんですって。
平賀源内の時代より1000年も前から、うなぎの夏バテ解消効果は知られていたんですね。
源内は、この古い知識を上手にマーケティングに活用したわけです。
豆知識3:現代でも年2回チャンスがある
土用の丑の日は、年によっては夏に2回あることも。
12日周期で丑の日が回ってくるので、18日間の土用期間中に2回当たることがあるんです。
その場合は「一の丑」「二の丑」って呼ばれて、うなぎ屋さんには2回稼ぎ時が来るんです。
まさに源内のマーケティング戦略の恩恵が現代まで続いているわけですね。
まとめ
土用の丑の日のうなぎは、江戸時代の平賀源内による見事なマーケティング戦略の成果だったんですね。
「売れない商品」を「特別な日の定番商品」に変えてしまう発想力。
既存の習慣に新商品を結びつけて、明確な理由づけをする手法。
これって、現代のマーケティング担当者も見習いたいアイデアです。
今度うなぎを食べるときは、300年前のマーケティングの成功事例を味わっているんだって思うと、また違った味がするかもしれませんね。
江戸時代の知恵って、本当にすごいですよね。