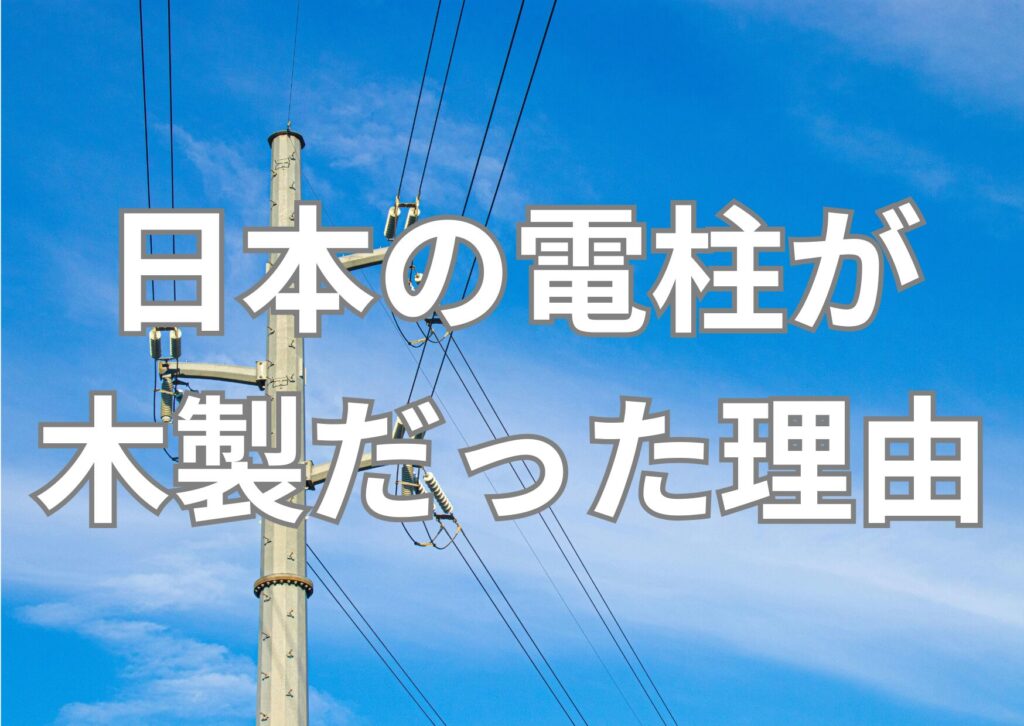日本の電柱って、昔は木でできてたって知ってました?
しかも今でも一部地域には木製電柱が残ってるんです!
でも「なんで木なの?コンクリートの方が丈夫じゃない?」って思いますよね。
調べてみたら、木製電柱には驚きの理由と秘密があったんです!
そもそも日本の電柱の歴史がドラマチックすぎた【明治の大変革】
電柱の歴史、これマジでドラマみたいなんです!
日本で最初に電気が使われ始めたのは明治時代。
1887年(明治20年)に東京電灯が家庭配電を開始したんです。
その時から電柱は木製が当たり前でした。
当時の木製電柱は真っ黒だったんです!
なぜかって?
防腐剤の「クレオソート」を高圧注入してたから。
古くなるとクレオソートが塊で浮き出てきて、独特の匂いがしてたそうです。昭和世代の人には懐かしい光景なんですよね。
宮沢賢治の童話「月夜のでんしんばしら」(大正10年)にも、電柱が兵士に変わって行進するシーンが出てきます。
当時の人にとって、どんどん増えていく電柱は近代文明の象徴だったんです!
なんで木製だったの?その理由がすごい【意外な合理性】
理由その1:日本は森林大国だから材料が豊富【地の利】
日本の国土の約70%は森林なんです!木材がとにかく豊富で安く手に入りました。
特に富山県では「ボカスギ」という電柱専用のスギ品種まで栽培してたんです。
電柱のために品種改良するって、すごくないですか?木製電柱がいかに重要だったかが分かりますね。
理由その2:加工しやすくて工期が短い【実用性抜群】
木って、切って防腐処理すればすぐ使えるんです。
コンクリートみたいに固まるまで待つ必要もないし、現場で長さを調整するのも簡単。
しかも軽いから運搬も楽!重機がない時代には、これがめちゃくちゃ重要だったんです。
理由その3:実は地震に強かった【柔軟性の勝利】
これ意外じゃないですか?
木って地震で折れちゃいそうなイメージですが、実は木材には「しなり」があるんです。
地震の揺れを柔軟に受け流して、ポキッと折れにくい。
しかも万が一倒れても、コンクリートほど重くないから被害が少ないんです。
理由その4:コストが圧倒的に安かった【経済的理由】
昭和初期にコンクリート製電柱が開発されても、しばらくは木製の方が安かったんです。
戦後復興で大量の電柱が必要だった時代、コストの安さは最重要でした。
じゃあなぜコンクリートに変わったの?【時代の変化】
変化の理由1:都市部の火災対策【函館の教訓】
1921年、函館で大火事が起きて2000軒以上が焼失しました。
木製電柱も燃えちゃって、電気復旧に時間がかかったんです。
そこで函館では1923年、日本初のコンクリート製電柱を設置!
これが現存する最古のコンクリート電柱で、今でも函館に残ってるんです。
しかも四角形なんですよ、技術的に円柱が作れなかったから。
変化の理由2:耐久性の問題【メンテナンス大変】
木製電柱の寿命は約30年。
クレオソートの防腐処理をしても、雨風で劣化しちゃうんです。
しかも定期的に防腐剤を塗り直す必要があって、メンテナンスが大変でした。
コンクリート製なら50年以上もつし、メンテナンスもほとんど不要。
長期的にはコスパが良かったんです。
変化の理由3:都市化で安全基準が厳しくなった【時代の要請】
都市部では建物が密集して、火災や感電のリスクが高まりました。
より安全で耐久性の高い電柱が求められるようになったんです。
えっ?今でも木製電柱があるの?【現代の木製電柱事情】
実は今でも日本各地に木製電柱が残ってるんです!
木製電柱が多い地域:神奈川県【意外な木製王国】
特に神奈川県の鎌倉や大船周辺には、木製電柱がたくさん残ってます。
観光地の景観を考慮して、あえて木製を使ってるところもあるんです。
北鎌倉の円覚寺や建長寺周辺では、歴史ある街並みに木製電柱がすごく似合うんですよね。
コンクリートだと無機質すぎて雰囲気が台無しになっちゃう。
なぜ今でも木製を使うの?【現代的な理由】
景観重視:歴史地区や観光地では、木製の方が自然で美しい
環境配慮:木材は再生可能資源で、CO2削減にも貢献
地域の特色:木製電柱そのものが観光資源になってる場合も
まだあった!電柱の面白すぎる豆知識【追い打ち情報】
豆知識1:世界では電柱自体が珍しい【日本は電柱大国】
実は欧米の主要都市では、電柱がほとんどないんです!
ロンドンやパリは無電柱化100%。
電線は全部地下に埋まってます。
日本は世界でも珍しい「電柱大国」。
なんと全国に3552万本もあって、毎年7万本も増えてるんです!
豆知識2:電柱登りの足場金具、覚えてる?【昭和の思い出】
昔の木製電柱には、L字型の金具が打ち付けられてました。
作業員が登るための足場だったんです。
子供の頃、あの金具を見て「登れそう」って思った人、多いんじゃないですか?
でも実際は超危険だから絶対ダメですよ!
豆知識3:宮沢賢治も電柱に魅了されてた【文学にも登場】
童話「月夜のでんしんばしら」では、電柱が兵士になって「ドッテテ、ドッテテ」のリズムで行進するんです。
電柱の普及に感動した賢治の想像力がすごすぎます!
大正時代の人にとって、整然と並ぶ電柱は本当に驚きの光景だったんでしょうね。
【まとめ】木製電柱の知られざる秘密、すごすぎた!
いかがでしたか?
木製電柱って、ただの古い技術じゃなくて、ちゃんと理由があったんですね!
今日分かったこと:
- 木製は森林大国日本にピッタリの合理的選択だった
- 地震に強くて加工しやすい優秀な材料
- 函館の大火がコンクリート化のきっかけ
- 今でも景観重視で木製電柱を使ってる地域がある
- 日本は世界でも珍しい電柱大国
今度電柱を見かけたら、「これ昔は木製だったんだよな」「神奈川にはまだ木製があるんだよな」なんて思い出しちゃいませんか?
鎌倉に行く機会があったら、ぜひ木製電柱探しをしてみてください。
歴史を感じられて、なかなか面白いですよ♪
次回は「なんでマンホールは丸いの?」の工学的理由を徹底調査予定です。
これもまた「なるほど〜」ってなる話ですよ!